ここ数日の、JICAの「ホームタウン制度」をめぐる混乱について思うことをざっと書きます。(まとまってません)
今回の件の発端は、タンザニア・タイムス紙の「Japan Dedicates Nagai City To Tanzania(直訳すれば『日本はタンザニアに長井市を寄贈する』)」という見出し。私は10年ほど前にタンザニアに留学させてもらっていたことがあるのですが、普段あまり見ない「タンザニア」という単語を急にこんなに目にするとは思わずびっくりしました。。 気になってタンザニアの他のニュース媒体も少し調べたところ、「ホームタウン制度」についてではありませんが、スワヒリ語ニュースの大手・Mwananchiにて、今年7月に『日本はタンザニア人に研修と雇用の扉を開く』と報じられているのを発見。
https://x.com/MwananchiNews/status/1946907947168121342
長井市長の「日本には雇用機会が多い一方で若者の数が少なく、退職者の数が若者を上回っている」という発言も紹介されていました。(ちなみに記事では長井市がナンガイ市になっていた) 上記の記事自体の是非はさておき、今回のホームタウン制度の趣旨は、あくまで国際交流や相互理解の促進であるとはいうものの、その先、あるいは元にはやはり「日本が直面する人口減少と人手不足という課題をどう解決するか」という点が少なからずあると思います。 既に外食産業やコンビニは外国人材なしでは成り立たないほか、公共交通をはじめとする様々な社会システムが人材不足によって機能不全に陥りつつあります。板橋でもバスの運転手不足が深刻で、乗客の多い路線ですら減便せざるを得ないような状況です。
また日本は、他国と比較した際の給与水準の相対的な低下により、国際的な人材獲得競争、特にいわゆる「外国高度人材」の獲得競争においては年々不利となっています。これからの日本を支えるためには、日本↔︎他国間の人の往来の戦略的促進と、高度人材含む外国人材の確保はやはり重要と思います。
しかし、先の選挙結果でも示された通り、こうした議論に対して「外国人を受け入れる前に、まずは日本人の雇用や生活の安定を優先すべきだ」という声が高まっているのが事実。実際に外国人と同じ地域で暮らしていれば、生活習慣や文化の違いから摩擦が生じることもままあるし、物価高で家計が厳しい中ですから、外国人への医療や生活保護等に税金が使われることに矛先が向き不満が生じるのも当然かもしれません。その上で今回の「ホームタウン制度」の炎上について、関係する政治家が単に誤解が生じた、反発が生まれた、この制度は国際交流や相互理解の促進にすぎない、と総括して終わるのは、やや怠慢ではないかと思います。
また、そもそも「国際交流や相互理解」に税金を投じること自体に疑問を抱き、「そんな曖昧なものに私たちの税金を使うべきではない」と考える方ももはや少なくないはずです。 国際交流や相互理解の促進が日本や相手国に何をもたらすのか、外国人材を受け入れると/受け入れをやめると日本社会はどうなるのか、国や自治体はどういった移民政策を打ち出し、その準備と対応はどのようにするのか。国民の不安・不満に正面から向き合い、懸念を解きほぐしながら、戦略的で現実的な議論をしなければなりません。
私自身は、移民の受け入れ促進は必要と考えています。もちろん、「生産年齢人口を維持するために誰でもかれでも受け入れる」というのではありません。国内だけでは補えない労働需要を見極め、その領域に対応できる人材に照準を合わせて受け入れ、日本社会に円滑に統合していく準備・対応が重要と思います。現状の日本の移民制度は、人材と仕事のマッチング、帯同者の労働市場へのアクセス、子どもの教育等々で課題がが多くあり、それらの改善も必須です。 今回の「ホームタウン制度」を活用し交流を深め、自然な人の往来を促すことは、自治体レベルで上記を実践する有効な方法のひとつになり得ると思います。アフリカは若年人口も資源も豊富で経済成長を続ける地域であり、日本の将来にとって重要なパートナーです。
また、不安定な国際情勢を踏まえれば、安全保障の観点からも他国との人的交流や関係強化は疎かにすべきではありません。日本にとってアフリカとの関係構築は、単なる「慈善事業」ではなく、戦略的な投資であると思います。 昨今外国人の権利と日本人の利益は対立軸で捉えられがちですが、本来両立し得るもの。日本人と外国人が共に安心して暮らし、学び、働ける環境をつくることは次世代への責任です。頑張ります!


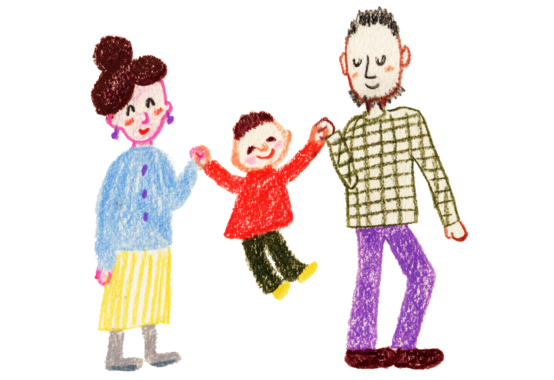

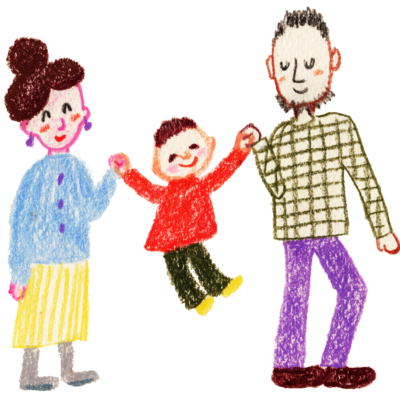







この記事へのコメントはありません。